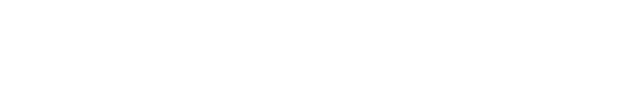第2の心臓と心腎連関
では、質問です。体の中で「第2の心臓」と呼ばれているのはどの部位でしょうか。
意外に思われるかもしれませんが、一般的な正解は、ふくらはぎです。ふくらはぎは、筋肉をポンプのように動かすことで、足先の血液を心臓まで戻すといわれています。血液を通す静脈の内側にはいくつもの弁があり、血液をスムーズに押しやり、また、逆流を防いだりしています。ちなみに、この弁がうまく働かなくなると、血液の通過障害が起こり、瘤(こぶ)ができます。これが、下肢静脈瘤(りゅう)で、皮膚表面に血管が浮き上がったように見えます。
さて、先程、第2の心臓と呼ばれる部位について、「一般的な正解は」と前置きしました。というのも、私は、ふくらはぎより、むしろ腎臓のほうが、第2の心臓と呼ぶのにふさわしいと考えているからです。
心臓と腎臓は、同じ循環系を司る主要臓器で、互いに大きな影響を及ぼし合います。たとえば、腎機能障害や蛋白尿は、心血管疾患の重大なリスク因子であることや、心機能が低下すると、腎血流の低下や腎臓の静脈圧上昇、神経やホルモンのバランス変化などにより、腎機能を低下させることなどが明らかになっています。私たちは、これを心腎連関と呼び、実臨床において常に意識する必要があります。
今秋、山口県で、慢性腎臓病対策として、心腎代謝診療医制度が導入されました。私自身、心腎代謝診療医として、これまで同様、心臓と腎臓をあわせて評価し、患者さんの心腎連関を守る視点での診療を心がけています。