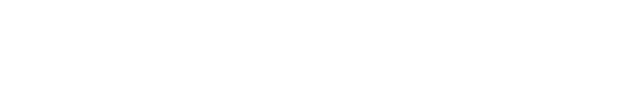タンパク質をめぐる糖尿病と慢性腎臓病
バランスよく栄養をとることは、健康長寿を実現していくための大切な習慣とされます。ただ、治療中の病気によっては、あえて栄養のバランスを崩し、特定の栄養を通常より多く摂取したり、逆に制限したりする必要がでてきます。
ここで、炭水化物、脂質と並ぶ3大栄養素の1つ、タンパク質に注目してみます。タンパク質は、体内で、筋肉や皮膚、内臓、ホルモンの材料やエネルギー源として用いられます。
糖尿病では、一般に、血糖を上げる炭水化物の摂取を控えなければならず、その分タンパク質を多くとることが勧められます。なお、動物性のタンパク質を取り過ぎると、糖尿病発症リスクになるとの報告もあり、動物性のうちでも鶏肉や魚といった、いわゆるホワイトミートや、植物由来のタンパク質を意識して選ぶことが求められます。
一方、糖尿病の代表的な合併症として、腎機能障害があります。慢性腎臓病では、腎保護の観点から、タンパク質を制限する考え方が広く実臨床で採用されています。ただ、糖尿病に対し、糖質を制限した上で、更に慢性腎臓病に対し、タンパク質制限をすると、筋肉量が低下するなどし、サルコペニアやフレイルの原因となってしまう恐れもあります。
いまの自分に、どの栄養がどの程度必要なのか、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。